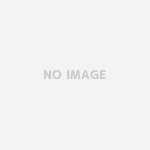パワハラは、法律用語ではありません。
法律用語でないというのは、法律で定義されていないということです。
そのため、パワハラへの対応には、個々の法律に基づくしかありません。
それは民法、刑法、労働基準法であったり、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律であったりします。
【1】パワハラは法律用語ではない
パワハラは、法律で定義されたものではありません。
たとえば、いじめについては、次のように法律で定義されています。
(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
法律上、定義されているということは、いじめの定義に該当すれば、一定の法律効果が生じるということです。
法律要件に該当すれば、法律効果が生じます。
法律効果が生じないなら、そもそも法律を制定する意味がないのですから当然です。
さて、パワハラについては、法律上の定義ではありません。
そのため、何がパワハラに該当するのかについては、明確な基準はありません。
また、パワハラに該当したからと言って、何か明確な法律効果が生じるわけではありません。
個々の法律に基づいて、判断されることなのです。
【2】個々の法律で対応するしかない
個々の法律というのは、たとえば民法、刑法、労働基準法、労働災害補償保険法などです。
パワハラを理由に損害賠償請求をする場合は、多くの場合は民法に基づきます。
会社に対して415条に基づいて損害賠償請求をするか、加害者に対して709条に基づいて請求をするのが一般的です。いずれにしても、パワハラであることを理由に請求をするのではなくて、安全配慮義務違反や、不法行為などによる損害賠償を請求します。
警察に動いてもらおうとすれば、刑法(刑事法)に基づいて請求をしなければなりません。実際に動いてくれる可能性は低いですが、侮辱罪、名誉棄損、強要罪、暴行罪などが該当しやすいでしょう。なお、故意に人を病気にさせた場合には、傷害罪に該当します。傷害罪は、人を傷つけることだけでなく、病気にすることも含むのです。
労働災害補償保険法は、たとえば、パワハラによって(業務上)うつ病に罹った場合などに関係してきます。
【3】行政ごとに、パワハラの定義が違う
上記のとおり、パワハラについて、法律上の定義はありません。
そのため、パワハラであるかどうかよりも、それぞれの条文に該当するかどうかが中心となります。
しかし、実際にパワハラと立ち向かうときに役立つのは司法ではなくて、行政です。
行政というのは、労働局であったり、警察であったりです。
パワハラにおいて、特に私達に関係が深いのは労働局でしょう。
労働局は、パワハラに関する相談を受けてくれる、行政機関の1つです。
労働局を管轄するのは厚生労働省であり、厚生労働省はパワハラを次のように定義しています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
これが最も有名なパワハラの定義ですが、これは厚生労働省の定義です。
法務省は、次のように定義しています。
「職場内での地位や
権限を利用したいじめ」を指し、「職権などの優位にある権限を背景に、本来の業務範囲を超え、継続的に、相手の人格と尊厳を侵害する言動を行い、就労環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」
法務省の定義では、継続性が必要となります。
また、身体的苦痛または精神的苦痛では足りず、人格と尊厳を侵害する言動が必要となります。
国家公務員のパワハラ相談先である人事院は、次のように定義しています。
「職務上の地位や権限又は職場内の優位性を背景に、業務の適正な
範囲を超えて、人格と尊厳を侵害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、あるいは職場環境を悪化させること」
厚生労働省と法務省の折衷案のような定義ですが、厚生労働省の定義に”人格と尊厳を侵害する言動を行い”という追加の定義があるため、条件は厳しくなっていると言えます。
さて、ここで大切なことは、法律による定義がないために行政はそれぞれに定義を出しているということです。これは、行政機関に相談に行くときには、それぞれの相談機関が出している定義にそってパワハラを主張しなければならないことを意味します。
【4】相談先の「パワハラ」の定義を調べよう
多くの場合、行政機関は被害者に寄り添って話を聞いてくれます。
ただし、行政の基本的立場は中立であり、あなたの味方になることはできません。
しかし、それがパワハラに該当するとなれば、それを無視することはできなくなります。
法律上、DVだと認定されたら、警察も無視できないのと同じです。
行政は、法律に書かれたとおりに動かなくてはなりませんし、上級機関の命令通りに動かなくてはなりません。そのため、上級庁が大々的に発表しているパワハラの定義に該当した事例を知りつつ、それを無視することはできないのです。
ですから、少なくともあなたはパワハラの定義に沿っていることを確認しましょう。そして、パワハラだと思うから支援をしてほしいと主張するようにしてください。
詳しい法律知識は必要ありません。法律は、読んでとおりに意味を取ること(文理解釈)が基本です。常識的に考えて、パワハラの定義に当てはまれば、それはその省庁にとってはパワハラです。
パワハラが法律上、定義されていないこと。そのため、パワハラに該当するとしても、必ずしも違法ではないこと。各行政機関が、それぞれにパワハラの定義を出していること。これらについて知っておけば、法律については十分だと思います。後は、それぞれの事例において、判断していくのがよいでしょう。法律上の定義はないこと、各行政機関が定義を出していることだけは、ぜひ覚えておいてください。